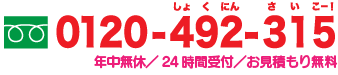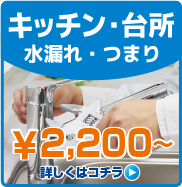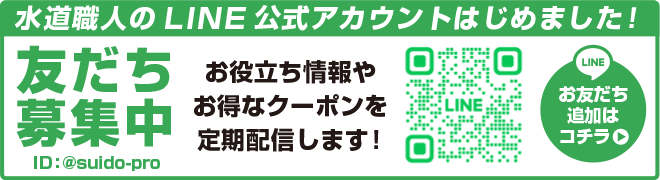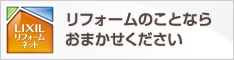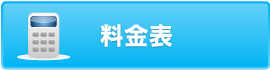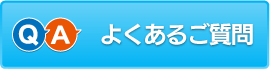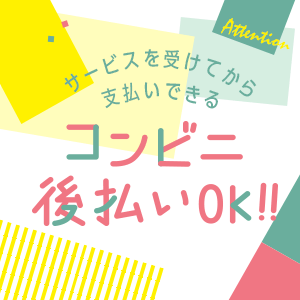水のコラム
「お花摘み」ってどういう意味?トイレにまつわる言葉の由来と文化【水道職人:プロ】

「お花を摘みに行ってきます」
こんな言葉、聞いたことはありませんか?
可愛らしい表現ですが、実は「トイレに行くこと」を指す言葉で、基本的には女性が遠回しに伝えるためによく使われてきました。
最近では、ほとんど日常会話で耳にしなくなったものの、「お花摘み」という表現が生まれた背景や、日本ならではのトイレにまつわる言葉の文化を知ると、ちょっとした発見があるかもしれません。
この記事では、「お花摘み」という言葉の由来や、日本独特のトイレの表現、また海外のユニークな言い回しなどについてもご紹介します。
普段何気なく使っている言葉も、その意味を知ると面白く感じるものです。
ちょっとした雑学として、ぜひ楽しみながら読んでみてください。
「お花摘み」ってどういう意味?

「お花摘み」という言葉には、どこか優雅で可愛らしい響きがありますよね。
冒頭でも書きましたが、昔から使われている「トイレに行くこと」を遠回しに表現した言葉のことです。
特に、女性が上品に伝えたいときに使われることが多く、日本ならではのやわらかな言い回しとして知られています。
では、どうして「お花摘み」という表現が生まれたんでしょうか?
由来としては諸説ありますが、一般的に有力な説としては、登山家たちの間で使われていたという説です。
山歩きの途中、女性が少し席を外す際に、「お花摘みに行ってきます」といった風に言い換えたことから、次第に広まったのではないかといわれています。
一見すると花を摘んでいるような姿にも見えることから、この表現の由来になったのかもしれませんね。
今ではあまり耳にすることはなくなりましたが、昔の小説や時代劇の中では時折見かけることも…。
意味を知っていると、古い作品を読むときの楽しみが増えるかもしれませんよ。
日本ならではのトイレに関する表現

日本では、昔から「トイレ」という言葉をそのまま使わず、やわらかい表現に言い換える文化があります。
「お花摘み」もそのひとつですが、ほかにもさまざまな言葉が生まれ、時代とともに変化してきました。
お手洗い・化粧室
「お手洗い」という言葉は、今でも広く使われていますよね。
もともとは、「手を洗う場所」を指していましたが、響きがやわらかく上品なため、トイレの言い換え表現として定着しました。
同じように、「化粧室」も女性向けのトイレを指す際に使われることが多く、ホテルや百貨店などでは「トイレ」よりもこの言葉がよく見られます。
御不浄・雪隠
少し昔にさかのぼると、「御不浄(ごふじょう)」という言葉も使われていました。
「不浄」という言葉には、「汚れ」や「けがれ」といった意味がありますが、そこに「御(お)」をつけることで、やわらかい印象にしているのが特徴的です。
江戸時代などでは、武家や商人の間でこの表現がよく使われていたといわれています。
また、寺院では「雪隠(せっちん)」という表現も使われていました。
これは、トイレが建物の隅に目立たないように配置されていたことから生まれたとされます。
昔の日本建築では、トイレは人目につかない場所に設置されることが多く、それがこの言葉の由来につながっているのかもしれません。
近年では「お花摘み」のような古風な表現は少なくなりましたが、時代に合わせて新しい言葉が生まれ続けているのも、日本語の面白いところですよね。
海外ではどう言う?世界のトイレフレーズ

実は、日本の「お花摘み」と同じように、海外にもトイレに関する直接的な言葉を避ける文化はたくさん存在します。
ただ、その表現の仕方は国によってさまざまで、それぞれの言語や生活習慣が反映されているのが面白いところです。
たとえば、英語では「restroom(レストルーム)」や「powder room(パウダールーム)」といった表現がよく使われます。
「restroom」は、直訳すると「休憩室」ですが、アメリカでは公共の場で一般的に使われる言葉です。
一方、「powder room」は、女性専用のトイレを指す言葉として、ホテルやレストランなどで見かけることが多いですね。
英語圏では、「I’m going to freshen up.(ちょっとさっぱりしてきます)」のように、遠回しに伝える表現もよく使われています。
これは、日本の「お花摘み」に通じるやわらかい言い回しといえるかもしれません。
またフランスでは、「les toilettes(レ・トワレット)」が一般的ですが、カフェやレストランでは「les petits coins(レ・プティ・コワン)」という表現を使うこともあります。
これは「小さな隅」という意味で、日本語の「ちょっと席を外します」に近い感覚で使われているそうです。
他にも国によっては、さらに個性的な表現もあります。
・イギリス「loo(ルー)」:トイレを指すスラングで、その語源には諸説ありますが、フランス語の「l’eau(水)」からきているともいわれています。
・オーストラリア「dunny(ダニー)」:昔の屋外トイレを指していた名残だそうです。
こうして世界のトイレ表現を見てみると、どの国でもトイレに関する表現は、その時代や場所に合わせてやわらかく、時にはユーモアを交えた表現が使われていることがわかりますね。
言葉から見るトイレ文化の奥深さ

普段、何気なく使っている言葉の中には、長い歴史や文化が隠れていることがあります。「お花摘み」もそのひとつ。
使われる機会は減ったものの、言葉の背景を知ることで、日本語の豊かさ、表現に込められた思いや工夫などを感じることができます。
こうした言葉の変遷を知ることは、単なる雑学としてではなく、言葉を大切にする日本の文化や、美しい表現を楽しむ心を思い起こさせる機会にも繋がります。
言葉は時代とともに変わるものですが、こうした文化や感性は風化させずに残していきたいものです。
ぜひ皆さんも「お花摘み」という言葉を、どこかでひっそりと使ってみてください。
監修者

福田マネージャー
《略歴》
2018年に株式会社 N-Visionに入社し水道メンテナンス業務を行う。
業界歴は7年で現在年間600件ほどの対応を行う。つまり・水漏れのトラブル解決のプロフェッショナルです。
修理完了後も安心してご利用いただける環境づくりに努めております。
福岡県でつまり・水漏れでお困りでしたらふくおか水道職人にお任せください。
福岡のトイレのつまり・水漏れは、水道修理の専門店「ふくおか水道職人(福岡水道職人)」
北九州市
福岡市
大牟田市
久留米市
直方市
飯塚市
田川市
柳川市
八女市
筑後市
大川市
行橋市
豊前市
中間市
小郡市
筑紫野市
春日市
大野城市
宗像市
太宰府市
古賀市
福津市
うきは市
宮若市
嘉麻市
朝倉市
みやま市
糸島市
筑紫郡那珂川町
糟屋郡
遠賀郡
鞍手郡
嘉穂郡桂川町
朝倉郡
三井郡大刀洗町
三潴郡大木町
八女郡広川町
田川郡
京都郡
築上郡
その他の地域の方もご相談ください!